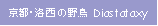アオサギの巣材運び - 1km以上先へ
4月上旬、京都・洛西(らくさい)の平地で、アオサギ Ardea cinerea を観察しました。
少なくとも1kmは飛ぶ
市街地の20mほど上空を飛ぶアオサギを見つけました。 そのアオサギは巣材をくわえていました。 見つけたところから1kmほどは追跡できたのですが、建物の陰で見えなくなりました。 その先はさらに1km以上も林はありません。 ほとんどのアオサギは木の上で営巣しますが、巣のそばではなく、巣から1km以上もはなれた場所から巣材を調達することもあるようです。

|
| アオサギが巣材をくわえて飛ぶ |
|
|
河原のアレチハナガサ類か
くわえ取った枝はUの字形に曲がっています。
Uの字の両側とも上向きに枝が出ています。
よって、これはUの字の底でつながっている二本の枝であることが分かります。
二本の枝からはさらに枝分かれしていますが、分かれ出ている細い枝は二本が対になって出ていますので、いわゆる「対生(たいせい)」の植物です。
この辺りに生えている、アオサギの全長よりも長い枝の、対生の植物としては、木ではなく草のアレチハナガサ類が考えられます。
アレチハナガサ類としますと、細い枝は花のついていた枝、すなわち花序(かじょ)ということになります。
Uの字の底でつながっている二本の枝は、地上からたくさん枝分かれして出た、株立(かぶだち)のうちの二本です。
アオサギはこのような状態で落ちていたこの枝をくわえて来たのか、あるいはまだ地面から生えた状態で枯れていたものをアオサギが引き抜いたところ、もう一本付いてきたのか、といったところでしょうか。
洛西では、アレチハナガサは河川敷や道端に生えています。
水辺で主にえさを取るアオサギが、よく訪れる場所のそばで巣材を取ったのでしょうか。
< 関連ページ >
![]() 調べる "アオサギ" ※ アオサギのその他の topic はこちらへ
調べる "アオサギ" ※ アオサギのその他の topic はこちらへ
![]() 調べる - テーマ別 "繁殖・営巣・造巣・巣作り" ※ その他の鳥の繁殖などはこちらへ
調べる - テーマ別 "繁殖・営巣・造巣・巣作り" ※ その他の鳥の繁殖などはこちらへ
2025.10.23